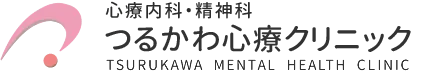不眠障害(不眠症)
不眠障害は、睡眠に関する問題の中で最もよく知られています。「寝つきが悪い」「途中で目が覚める」「朝早く目が覚めてしまう」「ぐっすり眠った感じがしない」といった症状が、適切な睡眠の機会があるにもかかわらず続き、日中の活動に支障をきたしている状態です。
DSM-5(精神障害の診断・統計マニュアル第5版)では、これらの症状が週に3回以上、3ヶ月以上にわたって続く場合に不眠障害と診断されることがあります。日本人の約5人に1人が何らかの睡眠問題を抱えていると言われ、非常に身近な病気です。
不眠の4つのタイプ
- 入眠障害:ベッドに入っても30分~1時間以上寝付けない。
- 中途覚醒:夜中に何度も目が覚め、その後なかなか寝付けない。
- 早朝覚醒:起きたい時間より2時間以上早く目が覚め、再入眠できない。
- 熟眠障害:睡眠時間は足りているはずなのに、眠りが浅く熟睡感がない。
これらの夜間の症状に加え、日中の眠気、倦怠感、集中力低下、気分の落ち込みなどが現れることも特徴です。
過眠障害
夜間に十分な睡眠時間(例:7時間以上)をとっているにもかかわらず、日中に過剰な眠気を感じ、日常生活に支障をきたす状態です。居眠りを繰り返したり、一度眠ると1時間以上続く長い昼寝になったり、目覚めてもスッキリしないといった特徴があります。ナルコレプシーや特発性過眠症などがこれに含まれます。
概日リズム睡眠・覚醒障害群
私たちの身体に備わっている体内時計(概日リズム)が、地球の24時間周期とずれてしまうことで起こる睡眠の問題です。以下のようなタイプがあります。
- 睡眠・覚醒相後退型:極端な夜型。深夜から明け方にならないと眠れず、朝起きられない。
- 睡眠・覚醒相前進型:極端な朝方。夕方や夜の早い時間に眠くなり、早朝に目覚めてしまう。
- 交代勤務型:夜勤など不規則な勤務により、体内時計が乱れてしまう。
むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)
夕方から夜にかけて、じっと座っていたり横になったりしていると、脚(時には腕などにも)に「むずむずする」「虫が這うような」「火照るような」といった不快な感覚が現れ、「脚を動かしたい」という強い衝動にかられる病気です。この症状のために寝付けず、不眠の原因となることがあります。鉄欠乏などが原因の一つと考えられています。
睡眠障害の治療
睡眠障害の治療では、まず原因を特定することが重要です。うつ病や不安障害などの精神疾患、あるいは身体の病気が隠れていることも少なくありません。当院では、丁寧な問診により原因を探り、患者さまに合った治療法をご提案します。
1. 睡眠衛生指導
良い睡眠を得るための環境や生活習慣についてのアドバイスです。規則正しい生活リズムを心がけ、寝室の環境を整え、適切な食事や運動習慣を身につけることが基本となります。
2. 認知行動療法(CBT-I)
特に不眠障害に対して、第一に推奨される治療法です。睡眠に対する誤った思い込みや習慣を修正し、正しい知識を身につけることで、睡眠薬に頼らずに不眠の改善を目指します。当院でも、必要に応じて心理カウンセリング(臨床心理士)と連携して対応します。
3. 薬物療法
症状が重い場合や、他の治療法で改善が見られない場合に、医師の判断のもとで睡眠薬などの薬物療法を検討します。睡眠薬には様々な種類があり、患者さまの状態に合わせて適切な薬を選択します。依存性や副作用のリスクを考慮し、必要最小限の量と期間で使用することを原則とします。自己判断での服薬や中断はせず、必ず医師にご相談ください。
4. 原因疾患の治療
不眠の原因となっている病気(うつ病、不安障害、むずむず脚症候群など)がある場合は、その治療を優先的に行います。